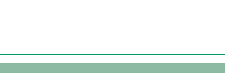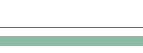伝統と文化「能と狂言」3
投稿日:2015年07月28日 09:00
◆伝承
650年もの間、脈々と親から子へ、子から孫へ、また、師匠から弟子へと
一度も絶えることなく伝え続けている演劇は、世界中でも日本の能や狂言が
唯一であると言っても過言ではないでしょう。
能楽は、2001年5月、パリのユネスコ本部において、第一回「人類の口承
及び無形遺産の傑作の宣言」を受け、更に2008年11月、無形文化遺産保護条
約に基づく「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に初めて登録され、後
世に伝えるべき貴重な財産として広く世界の認定するところとなりました。
◆能の役割
シテとは、主役のことで、仕手、偽手などの字を当て、演技する人をさし
ていました。前後二場から成る能では、前シテ、後シテと呼び分けます。多
くの曲は、前シテが里人など仮の姿で現れ、後シテで本性を現すものですが、
前後で別人格を演ずる曲もあります。
ワキとは、シテの相手役で脇とも書きます。僧・神職・大臣などの役柄が
多く、シテは亡霊・化身・精など次元を超えて自在に設定されていますが、
ワキは現実に生きている男性の役です。まれにワキの登場しない曲もありま
す。
ツレとは、連れ合う者の意味で助演者です。シテツレとワキツレがあり、
単にツレと表す時はシテツレの事です。前・後場で役柄が変わり、前ツレ、
後ツレと分ける事もあります。また、ツレが登場しない曲もあれば、二人以
上登場することもあります。
ワキツレとは、ワキの助演者でワキ方が担当します。
間狂言とは、能とは別に「狂言」として成立している演劇がありますが、
能の中に登場する狂言を「間狂言」と呼び、登場人物を紹介したり、舞台の
展開を説明したり、時には面白おかしくストーリーを盛り立てる役もこなし
ます。多くは、前場と後場をつなぐ役割として活躍します。
後見とは、舞台の進行が円滑に運ぶよう見届ける役割で、装束を直したり、
作り物や小道具の受け渡し役を務めるほか、シテに万一事故があったとき、
直ちに代役を演じなければならないために大変重要な役割です。それゆえ、
特に後見のリーダーである主後見の役はシテと同格か、演目によってはシテ
より上位の者が担当することが多くなっています。
地謡とは、一種の合唱隊で舞台右の地謡座に座り、通常は前後四名ずつ計
八名が並びます。情景や登場人物の心理を謡で表します。後列中央に座って
いるのが地頭で地謡のリーダーです。
囃子とは、楽器を演奏する役で笛・小鼓・大鼓・太鼓が、それぞれ一人ず
つ、計四人で囃します。この囃子方と後見、地謡は登場人物でないので装束
はつけずに紋付袴で登場します。
◆狂言の役割
シテとは、主役のことです。アドとは、シテに対する相手役、脇役のこと
です。後見とは、能同じく、いわば舞台の進行役で重要な役割です。
地謡とは、謡の合唱隊で能の地謡とは違い、地謡座には座らずに後座に居
並びます。囃子とは、能とは違い、床几には座りません。笛・小鼓は正面か
ら見て左向きに、大鼓・太鼓は右向きに横を向いて座ります。
◆能舞台
能舞台はもともと屋外につくられており、現在のように舞台と観客席とが
大きな一つの建物の中に入った「能楽堂」という形になったのは明治以降の
ことです。薪能・奉納能などに代表されるように、能は本来、何処でも上演
が可能ですが、演目などによっては本格的な能舞台が理想的である場合もあ
ります。
★奉納 第二十五回「八ヶ岳薪能」身曾岐神社
http://www.just.st/index.php?tn=index&in=302069&pan=6845
★鶴見隆史医師監修のNEWシリーズ!
体の隅々まで大きな抗酸化力を発揮する「鶴見式水素」
http://www.lifestyle.jp/turumisuiso.html

https://www.lifestyle.co.jp/2015/07/3_4.html
|